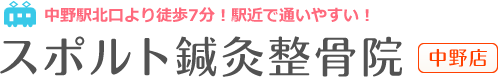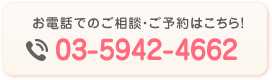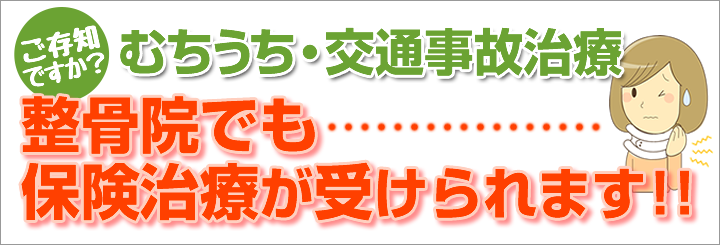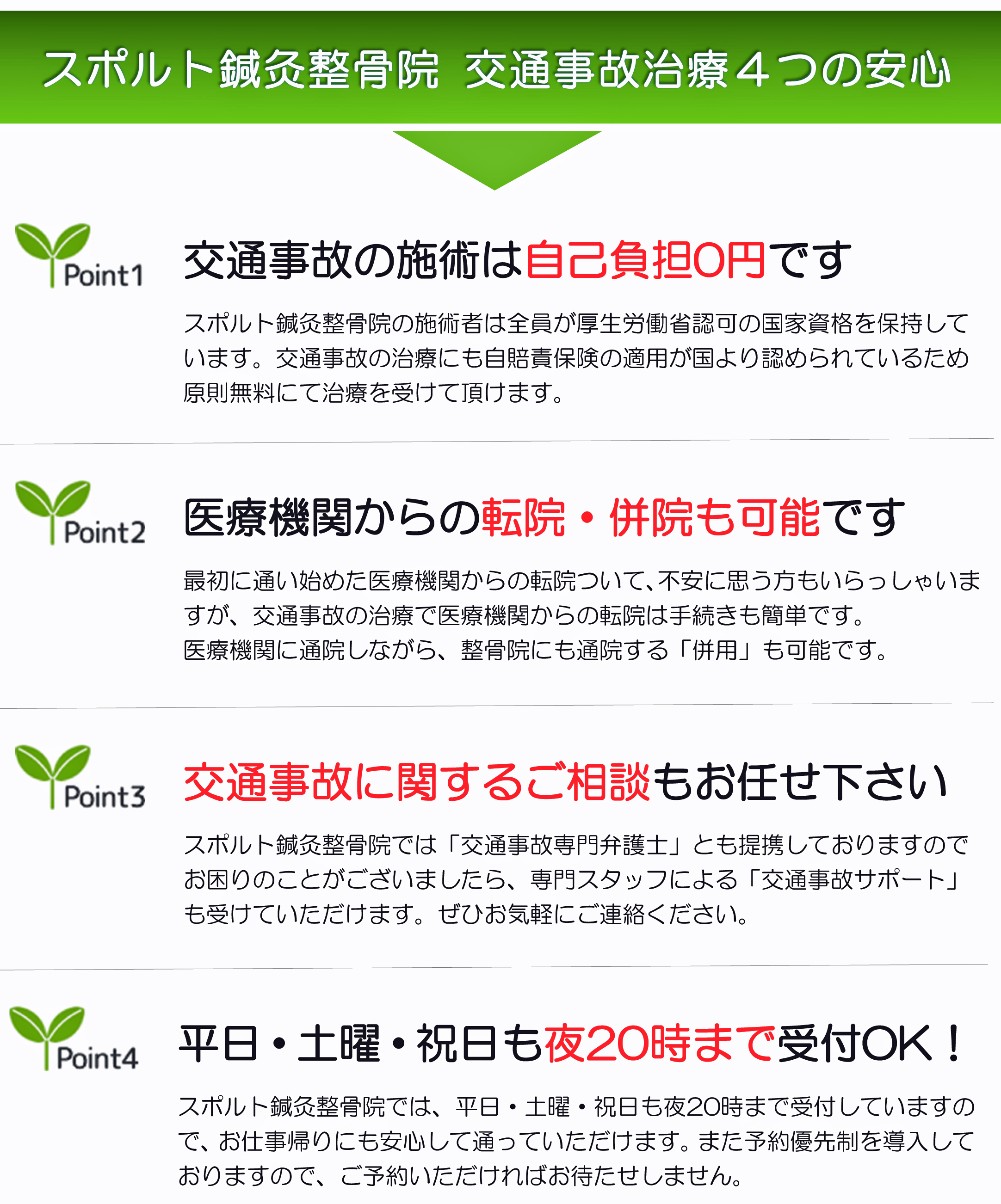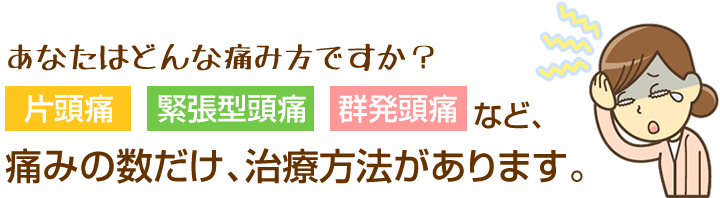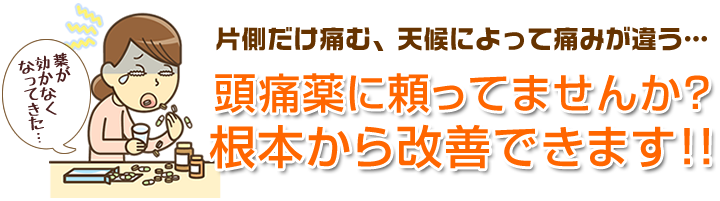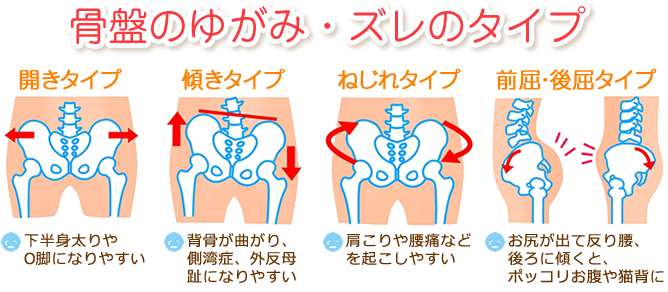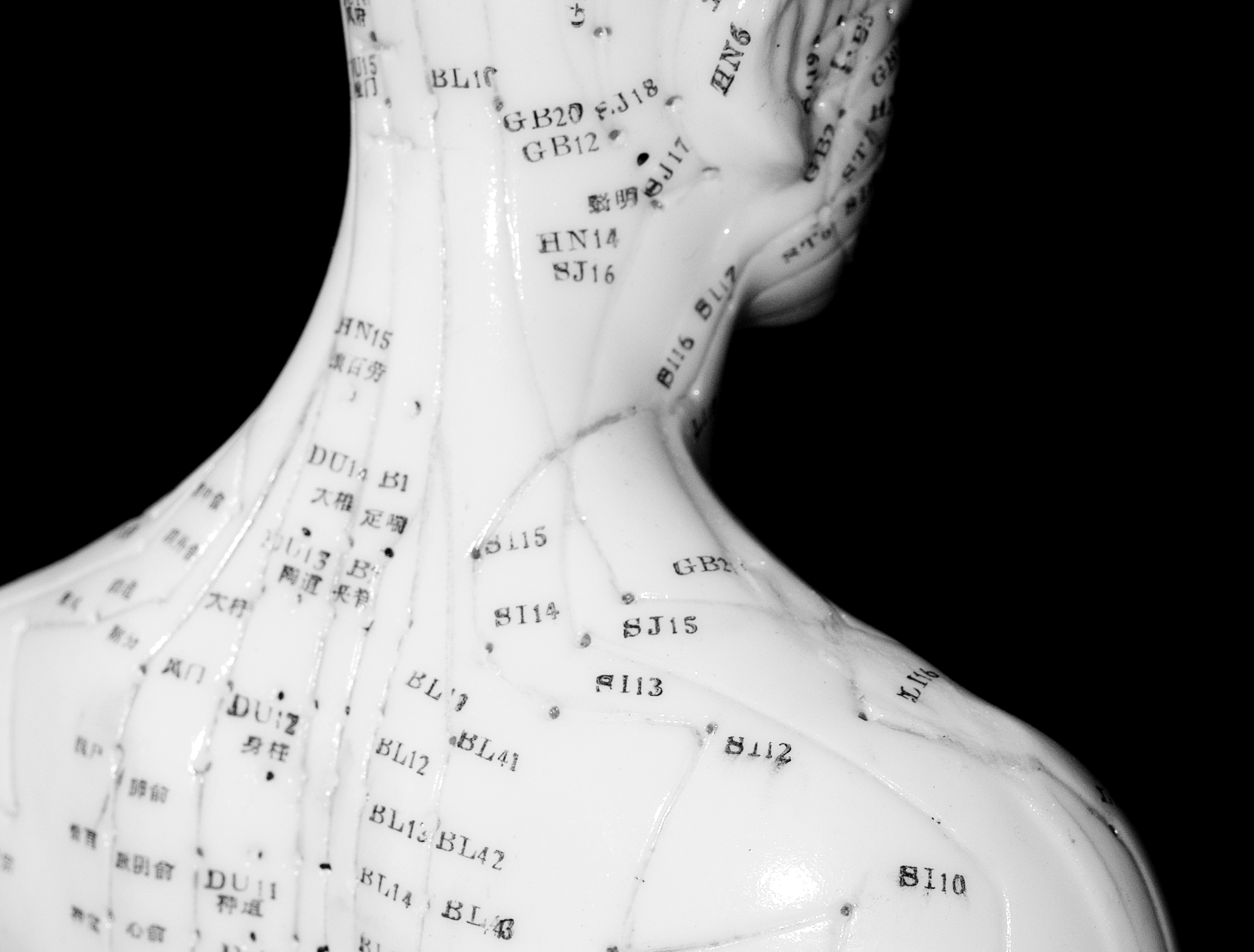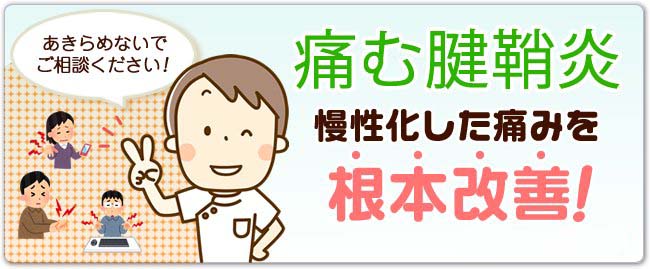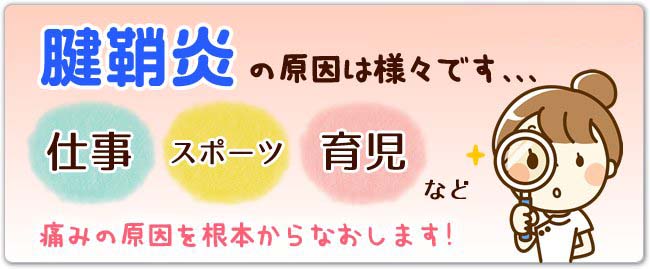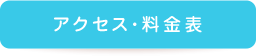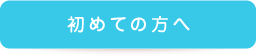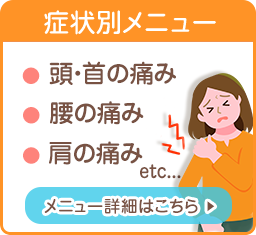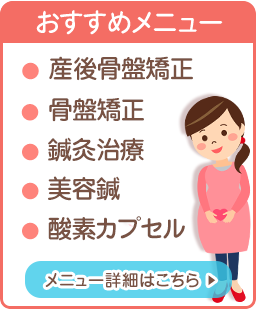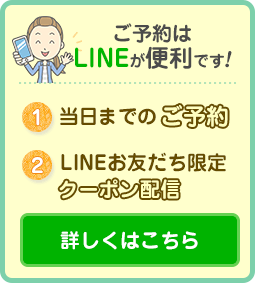交通事故治療のメリット・デメリット〈中野の整骨院「スポルト鍼灸整骨院」〉
2023年11月9日
交通事故治療に関する問題点
こんにちは。中野の整骨院「スポルト鍼灸整骨院」です。
整骨院で交通事故治療を受ける際に、トラブルが発生することがあります。これらのトラブルを避けるために、注意すべきポイントを知り、正しい方法で治療を受けることが重要です。
以下では、整骨院での交通事故治療に関する問題点と解決策について詳しく説明します。
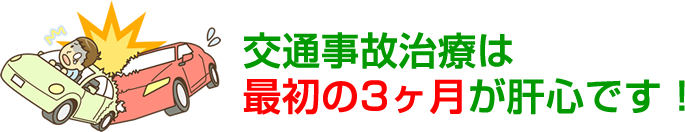
交通事故に遭ったら、まず整形外科を受診
交通事故に遭った際、保険会社が病院や整骨院の治療費を直接支払う、一括対応と呼ばれる仕組みがあります。
ただし、保険会社は一括対応を法的義務として行っているわけではなく、サービスの一環として行っています。
このため、保険会社の判断で一括対応を打ち切ることができます。
医師の許可なしに整骨院に通院した場合、一括対応を打ち切られる場合があります。
保険会社は整骨院での施術の必要性や有効性に疑念を抱くことがあり、それが一括対応の打ち切りにつながる事もあります。
また、過度な頻度で整骨院に通院すると、治療費が増加し、保険会社の打ち切りも早まる傾向があります。
解決策としては、交通事故の際は、まず医師の診断を受け、適切な治療計画を立てることが重要です。
医師の指導に従い、整骨院に通院する場合も医師の同意を得ることをおすすめします。
また、治療の必要性について保険会社と連絡を取り合うことも大切です。
負傷部位以外の施術は認められない
交通事故によるケガを証明するためには、医師の診断が不可欠です。
医師の診断がない部位に対する施術は、保険会社からの支払いが拒否される可能性があります。例えば、医師の診断が腰椎捻挫だけで、整骨院で腕の施術が行われた場合、腕の施術費用は事故との因果関係が否定されて賠償されないことがあります。
解決策として、交通事故に遭った際は、まず医師による診断を受けましょう。診断結果をもとに、適切な治療を受けることが重要です。
整骨院での施術を受ける際も、医師の診断をもとに治療計画を立て、関連部位の施術を行うようにしましょう。これにより、保険請求の際の不要なトラブルを避け、支払いの拒否を回避できます。
整骨院では診断書が書けない
整骨院では、診断書を発行できません。
診断書の代わりに、施術証明書が提供されます。しかし、後遺障害申請時には、医師が書いた「後遺障害診断書」が必要となります。
整骨院で通院している場合、後遺障害診断書を取得できず、後遺障害の認定が難しくなります。
解決策として、後遺障害診断書は医師によって発行されるため、整骨院で治療を受けた後、病院を受診して後遺障害診断書を取得することを検討しましょう。
この診断書は後の賠償請求に必要なものでもあり、整骨院での施術証明書と併用することが有益です。
後遺障害認定について
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構によって審査されます。
整骨院を中心に通院している被害者と病院を中心に通院している被害者を比較すると、病院での通院者の方が後遺障害認定が得られる傾向があることが報告されています。
これは、病院での通院が一般的に後遺障害の認定を容易にする要因とされています。
後遺障害の認定は一定の要件を満たす必要があります。医療機関の選択については慎重に行い、専門的なアドバイスを受けることが大切です。
整体院・カイロプラクティックでの治療は認められない
整体院やカイロプラクティックなどでの治療については、原則として賠償として認められません。これらは、国家資格を必要としない医療類似行為であり、その必要性や有効性が明確でないためです。
整体院やカイロプラクティックで治療を受ける場合、保険請求には制約があることを理解しましょう。
事前に保険会社と相談し、治療方法についての認識を確認し、適切な治療を受けるかどうかを検討して下さい。
交通事故に遭った際の治療は重要ですが、整骨院での治療に際しては、医師の診断や適切な証拠を収集し、保険請求を円滑に進めることが重要です。
また、後遺障害の認定や特定の治療方法についても十分な情報を収集し、適切な選択を行うことが大切です。
交通事故治療に関するトラブルを回避し、適切な治療を受けることで、早期回復と適切な賠償を得ることができます。