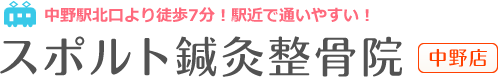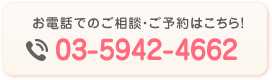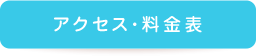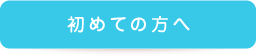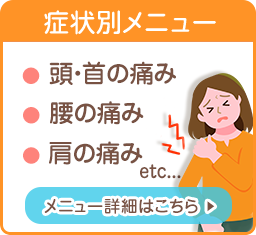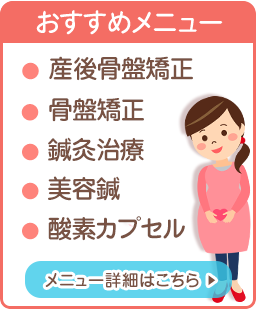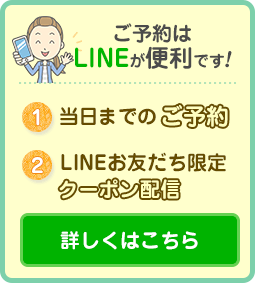顎関節症と肩こりの関係〈スポルト鍼灸整骨院 中野店〉
2022年11月30日
こんにちは。
中野区新井2丁目の「スポルト鍼灸整骨院 中野店」です。
今回は「顎関節症と肩こりの関係」についてお話しします。
【顎関節症とは】
顎関節症とは、顎関節や咀嚼筋の痛み、顎関節の雑音、開口障害、ないし顎の運動異常などの総称を指します。
これらのうち、少なくとも1つ以上該当することが顎関節症の基準とされています。
したがって、咬み合わせの違和感、耳の異常、頭痛、画像検査による異常などでは顎関節症とは認められません。
近年では、日中・夜間のくいしばりが特に注目されています。
精神的なストレスは筋肉の緊張を引き起こし、咀嚼筋や顎関節の負担を増やしている恐れがあるなど、さまざまな要因が影響しあって引き起こしていると言われています。
日常でストレスをため込むことなく、顎周りの習慣や癖を自覚し、それらを意識的に無くしていくことは、顎関節症を改善する上で重要です。

【顎関節症と肩こりの関係】
肩こりはさまざまな要因で発生しますが、顎関節症も肩こりを起こす要因の一つとされています。
顎関節症による顎のズレは頭の位置を微妙に変化させるため、体全体の重心に狂いが生じます。
重心が変わると都度バランスをとろうとするので、頭の傾きや頸椎の並びにも変化が起きます。これが首や肩に付着している筋肉に負荷をかけ、肩こりを起こしています。
姿勢も肩こりにつながる大きな要因です。
よくあるのは顎が前方へ突き出た姿勢で、人によっては猫背で背中が丸まって見えたりします。
この姿勢は体への負荷が大きく、首や肩の筋肉を緊張させることで肩こりにつながっています。

顎関節症が発生することで噛み合わせにも変化が出ます。
噛み合わせが悪くなることで顎周りから肩周りの筋肉に負荷がかかるようになり、それが悪化していくと耳鳴り・めまい・目の充血や痛み・手足のしびれなどが起きる可能性も高くなります。
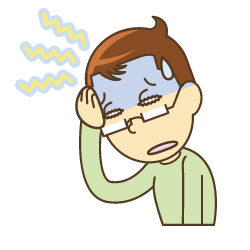
【まとめ】
顎関節症は不規則な生活の連続、疲労の蓄積などが要因となって起こります。
そこから肩こり、頭痛、耳鳴り、めまいなどにつながることも良くあります。
昨今なかなか同じ生活リズムで過ごすのは難しいですが、食事や睡眠をきちんと取ることで身体の回復につながるので、意識的に取り組むことが重要です。
また、顎関節症の改善には鍼施術も有効です。
顎関節症によって顎周囲や首肩の筋肉が硬くなっていくため、鍼によって血行を促し状態を緩和させることができます。
気になる方はぜひ一度ご相談ください。